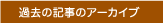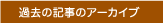
当法人では、令和6年度 職員募集をしております。下から入っていただき、詳細をご確認いただけます。「雰囲気を見てみたい」「仕事の内容を詳しく聞きたい」方も、WEB説明会や見学をお受けしております。
電話、メール(愛泉会ホームページ内、問い合わせ)よりご相談下さい。
(見学希望・お問い合わせ)
社会福祉法人愛泉会 法人本部
住所:山形市諏訪町一丁目2番7号
TEL:023-664-2117
採用担当:庄司・八柳・塚田
詳細は↓↓↓クリック↓↓↓
6月の法人内研修として、初任職員(3年目職員)対象研修と安全運転講習会を実施いたしました。
【初任職員(3年目職員)対象研修】
初任職員研修については、これまでは2~3年目という一括りで研修を実施しておりましたが、さらに学びを深めてもらうことを目的に、2年目と3年目で分けて研修を実施することといたしました。
今年度の3年目職員対象研修では、主体的に学んでいただくことを目的に、グループワークをメインとして研修を実施していく予定です。第1回目の研修では、昨年度までの研修内容の振り返りとこの1年間の研修内容について説明いたしました。

【安全運転講習会】
当法人では毎年、新規採用職員を対象に、安全運転講習会を実施しており、今年度も入職した4名の方を対象に講習会を開催いたしました。
この講習会は、運転業務を含め日々の業務において留意すべきことをお伝えし、安全に関する意識を高めることを目的に実施しており、今年度も約2時間の講義をとおして、それらをお伝えいたしました。
今年度も様々な研修を実施し、さらなるサービスの質向上およびソーシャルワークの実践につなげていきたいと思います。
令和6年度第1回新任職員研修を5/23(木)に実施いたしました!
愛泉会では、入職1~3年目の職員を対象にそれぞれ年5回程度で研修を実施しております。入職1年目の職員が対象となる「新任職員研修」では、ソーシャルワークの基本的な知識を学んでいただくことを目的に研修をおこなっております。
第1回目となる今回の研修は、ソーシャルワークにおいて最も基本的かつ重要である「価値と倫理」をテーマに実施いたしました。約2時間の研修の中で、演習も行いながら“価値とは?倫理とは?”について学びを深めていただきました。
6月からは、2年目、3年目を対象とした研修も始まり、他にも階層別の研修も実施予定です!今年もサービスの質向上を目指し、様々な研修を企画・実施してまいりたいと思います。
4/1(月)令和6年度社会福祉法人愛泉会入社式及び辞令交付式が法人本部会議室で執り行われ、今年度は、3名の職員が新たに採用されました。

理事長よりお話しを頂戴した後、4/1/・4/2の2日間にかけて法人として望むこと等を講話や映像、また事業所見学会をとおしてお伝えいたしました。
限られた時間ではございましたが、新規採用職員の皆さんに愛泉会について知っていただくことのできた時間になったかと思います。

今年度もソーシャルワークの実践に向けて、研修等を実施してまいりたいと思います。
令和5年度最後の新任職員研修および初任職員研修を実施いたしました!
年度の総まとめということで、新任職員研修では「自己覚知」をテーマに、そして初任職員研修ではグループワークを中心に研修を行いました。
新任職員研修では、1年間をとおしてソーシャルワークの基礎的な知識を学んでいただきましたが、最後となる今回の研修は「自己覚知」について講話を聞いていただきました。これまでの自らの業務や支援を振り返りながら、次年度以降につなげていただくために、このテーマを設定いたしました。
初任職員研修では、ケアマネジメントの実践というタイトルでグループワークを中心に、“思いを捉える”という演習を行っていただきました。1つの事例を用いて、言葉で把握している思いに限らず、本人のニーズを捉えるとういことをグループワークをとおして学んでいただきました。

今年度の新任および初任職員研修は、この回をもって終了となりましたが、次年度以降も他の階層別研修も含め、職員1人ひとりが学び、そしてソーシャルワークの実践につなげていくことができるように、研修を検討・実施してまいりたいと思います。
今年度、県から委託を受け、作品募集を行った「やまがたくだもの絵画コンクール」のラッピングバスのお披露目式が1/26(金)山形県庁にて行われました。当日は、山形県吉村美栄子知事もご出席され、知事のあいさつ、最優秀賞受賞者からのコメントの後、テープカットが行われました。
バスの両側面に入賞された5作品が配されており、山交バスと庄内交通が村山、最上、置賜、庄内で運行する各1台をラッピングしていました。様々なくだものが描かれたバスは、どの部分を見てもとても華やかでした。
この絵画コンクールは、知的障がいのある子どもたちの表現活動への意欲を高めるとともに、県民の障がい者への理解を促進することを目的に実施いたしました。今後も障がいのある方が地域で暮らし、働き、参加することのできる「地域共生社会」の実現を目指し、活動を実施してまいりたいと思います。

ラッピングバス

最優秀賞受賞作家 長濱哲哉さん
第4回初任職員対象研修を12月、1月に行いました!
今回は「意思決定 自己決定」をテーマとし、創造企画部八柳主幹より講話を頂戴いたしました。「意思決定 自己決定」、どちらもよく耳にする言葉ではありますが、改めて日々の支援を振り返りながらその言葉の意味を学んでいただくことを目的として、このテーマを設定いたしました。講話の後には「知的障害者の支援者のための意思決定支援ワークブック」(公益財団法人日本知的障害者福祉協会)から2つの事例を抜粋し、その事例をもとにグループワークを行い、ご本人の意思決定・自己決定をどのように支援していくべきかをグループ内で意見交換しながら検討してもらいました。

普段は異なる事業所で働ている同期間で意見交換することができ、参加者にとっても学びの多い時間だったかと思います。
今年度の初任職員を対象としたのも残り1回となりました。最後の研修も学びの多いものとなるよう、内容を検討してまいりたいと思います。
新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、昨年は新型コロナの感染類型が変わりましたが当法人では年末にかけても天童や中山のグループホームで感染があり、支援にあたっていただいたスタッフの皆さんに感謝申し上げます。
感染しないことに越したことはございませんがウィズコロナとなり私たちには地域社会との交流をとおしたより積極的な実践が求められていると考えます。
さて、愛泉会は今年で法人設立39年目となります。利用者50名 職員23名で始まった愛泉会は現在多くの方々にご利用いただき職員数は280名を超えています。当初は向陽園の中での活動や長谷堂地区での活動が中心でしたが、現在は山形市、天童市、上山市、中山町に拠点となる事業所を持つ法人規模となりました。
組織は大きくなるにつれて意思疎通が難しくなりますがそれぞれの事業所の独立性を高め、互いに同じ目標を持ち連携していくことが重要となっています。本日は昨年特に私の印象に残っている二つの出来事をお話ししたいと思います。
一つは昨年12月に仙台市で東北フォーラムインみやぎが開催されました。久しぶりの対面開催となりましたがその講演で重度心身障害者のあるご本人である高橋桃子さんとお母さんが講演されました。講演内容も素晴らしかったのですがさらに感心したのは、その行動の積極性で、2人でよく仙台の街にお買い物等でお出かけするそうです。心身に重い障害を抱える皆さんにとって一日一日が勝負でお母さんが桃子さんに豊かな経験をしてほしいと願いそのような積極的な行動につながっていることが理解できました。私たちも利用者にとってかげがえのない日々を送ることが出来るように実践の質を高めていきたいと思います。
二つ目は昨年9月に島根県にあるいわみ福祉会の50周年記念の会に参加いたしました。障害のある子どもを持つ母親である室崎富恵さんが理事長を務められています。当法人より10年程先に発足し法人規模は約2倍ほどです。
お伺いして驚くのは各事業所の質の高さです。障害者支援施設の桑の木園の生活環境の素晴らしさ、就労支援ABの規模の大きさと活動内容、障害者乗馬、レストラン経営、地元の民俗芸能であるいわみ神楽への取り組み、そして共通するのはスッタフの方の明るさと利用者がいきいきと働く姿が印象的でした。HPにアクセスしてみてください。私はこれまで圧倒的に障害福祉サービスが少ない山形で法人の規模の拡大で多くの人々にお役に立てることと支援の質を保っていくことは難しいと考え悩んできました。いわみ福祉会の実践は大きな驚きでした。今後私たち法人の目指す方向性の一つであると思います。
現在愛泉会では次の中長期計画の作成を予定しています。先日、なかやま虹の丘からは素晴らしい内容の提案をいただきました。是非皆さん方の想いや夢を提案いただきたいと思います。
結びに一昨年亡くなられた元向陽園の小林俊朗園長の口癖は「私たちの仕事はいったいだれのためにあるかを問うこと」でした。それを基にして現在の法人の基本理念である「人権の尊重」「自立支援」「受容と共感」や経営理念である「利用者中心」「地域貢献」「夢の実現」をつくりました。
今年一年そしてこれからも私たちの仕事が誰のためにあるかそれは当然、障害を持ちながら懸命に生きている利用者の幸せのためそしてご家族のためであります。
スタッフの皆さんにはそのことを胸に刻んで日々の仕事にあたっていただければ幸いです。
今年一年が皆さんにとって最良の年となりますようにお祈り申し上げます。簡単ですが年頭に当たってのごあいさつといたします。
令和6年1月4日
社会福祉法人 愛泉会
理事長 井上 博
11/24(金)、第3回新任職員研修を開催いたしました。
前回の研修に続き、アセスメントについて学んでいただくことを目的とし、講話とグループワークの2部構成で研修を行いました。
講話では、医学モデル、社会モデルについての説明を聞いていただき、それらを踏まえながらどのような点に留意しアセスメントを行う必要があるのかを学んでいただきました。
グループワークでは、これまでの業務を振り返っていただきながら、同期等で意見交換をしてもらいました。
今年度の新任職員研修も残り2回となりました。次年度に向けて、さらに職員1人ひとりが学び、成長できる職場となるように、研修内容を検討してまいりたいと思います。
愛泉会では各事業所にICT推進担当者を設け、今般の少子高齢化による労働人口減少への対応や、生産性(量・質)の向上により、より利用者支援の充実及び職員のライフワークバランスの充実を目指し、活動を行っております。
既存の業務フローの中でデジタル技術を導入する意義や、デジタル技術を用いることで、法人が所有する情報の共有や活用によって顧客、職員、法人がどのようなメリットがあるか等の見分を広げるべく、この度12月15日に株式会社メコムのDXセンターを見学し、顧客満足度向上や職員満足度向上に有効なソリューションや日々の業務フローの中でデジタル化を行うことで生産性向上につながる可能性のあるソリューション等をご紹介いただきました。
見学会には、各事業所のICT推進担当者等が出席いたしましたが、参加した職員からは“とても勉強になった”“こういうシステムが導入されたら、業務も効率化されサービスの質向上にもつながっていくと思った”といった感想が寄せられました。
今後もICT推進に関する諸研修や会議等を行いながら、より利用者支援の充実及び職員のライフワークバランスの充実を目指してまいりたいと思います。
総務課 田中